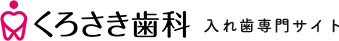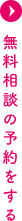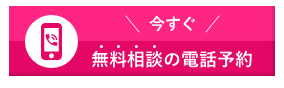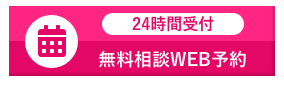【2026年最新】入れ歯の保険適用費用と相場〜徹底ガイド
入れ歯の保険適用とは?基本を理解しよう

入れ歯が必要になったとき、多くの方がまず気になるのが費用の問題です。「保険は使えるのか」「いくらかかるのか」という疑問をお持ちではないでしょうか。
入れ歯治療には、健康保険が適用される「保険診療」と全額自己負担の「自費診療」があります。両者には使用できる素材や設計に大きな違いがあります。
保険適用の入れ歯は、健康保険が適用される範囲で作製される入れ歯のことを指します。主にレジンと呼ばれるプラスチックの素材を使用し、日常生活に必要な最低限の機能と審美性を満たすことを目的としています。
保険診療のため、治療費の自己負担が抑えられる点が大きな特徴です。ただし、使用できる素材や設計には一定の制限があり、金属床や特殊な構造の入れ歯は対象外となります。
保険適用の入れ歯が選ばれる主な理由は、経済的な負担を軽減できる点にあります。高額な自費診療と比較して、費用を抑えながら必要な咀嚼機能を回復できるため、多くの方が選択肢の一つとしています。
保険適用される入れ歯の種類と特徴
保険適用される入れ歯には、大きく分けて「部分入れ歯」と「総入れ歯」の2種類があります。それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。
部分入れ歯の特徴と構造
部分入れ歯は、歯が一部だけ失われた場合に使われる入れ歯です。残っている歯に金属のバネ(クラスプ)をかけて固定する構造が一般的で、主にレジン(プラスチック)素材が使われます。
数本から多数の歯を失った場合まで幅広く対応でき、残っている歯の状態や本数によって設計が異なります。自分の歯を活かしながら噛む機能を補うことができる点が特徴です。
ただし、金属のバネが見えることがあるため、前歯に使用する場合は見た目を気にされる方もいらっしゃいます。また、バネをかける歯に負担がかかることもあるため、定期的なメンテナンスが重要になります。
総入れ歯の特徴と構造
総入れ歯は、上顎または下顎の歯が全部なくなった場合に使用されます。歯ぐき全体を覆う形で作られ、レジン(プラスチック)素材が用いられます。
歯が全く残っていない方が対象となり、歯ぐきや顎の形に合わせて製作されます。上顎の総入れ歯は吸着力が働くため比較的安定しますが、下顎の総入れ歯は舌の動きの影響を受けやすく、安定させるのが難しい傾向があります。
装着時の違和感や噛み心地に個人差がありますが、適切な調整で日常生活に支障なく使用できることを目指します。
使用される素材と制限
保険適用の入れ歯に使用される主な素材は、レジンと呼ばれるプラスチック材料です。部分入れ歯の場合は金属のバネが付くことが多く、総入れ歯は全体がレジンで作られます。
保険診療では素材や構造に一定の基準が設けられており、機能性と安全性を重視した設計となっています。見た目や使い心地、丈夫さといった点は自費診療の入れ歯と異なる点もあるため、治療については歯科医師と十分に話し合うことが欠かせません。
保険適用入れ歯の費用相場と治療の流れ
保険適用の入れ歯の費用は、種類や失った歯の本数によって異なります。2026年現在の相場について詳しく見ていきましょう。
部分入れ歯の費用相場
部分入れ歯は、失った歯の本数や部位によって費用が異なりますが、健康保険が適用される場合、3割負担でおおよそ5,000円から15,000円程度が一般的です。
使用できる材料や設計に制限があり、主にレジン(プラスチック)製のものが使用されます。金属バネで固定するタイプが多く、審美性や装着感に関しては自費診療の入れ歯と異なりますが、機能性は十分に考慮されています。
失った歯が多いほど費用は高くなる傾向にありますが、保険診療のため大きな差はありません。また、後期高齢者医療制度を利用している方は1割負担となるため、さらに費用を抑えることができます。
総入れ歯の費用相場

全ての歯を失った場合に作製する総入れ歯も、健康保険が適用されると自己負担はおおよそ3割負担で10,000円から20,000円程度が目安です。こちらもレジン床義歯が基本となり、材料や製作工程が保険の範囲内で決められています。
上顎と下顎の両方に総入れ歯が必要な場合は、それぞれの費用がかかりますので、合計すると20,000円から40,000円程度になることもあります。
費用には型取りや調整、完成後の微調整も含まれていますが、特別な素材や精密な設計を希望する場合は保険外となります。
治療の流れと期間
保険適用の入れ歯治療は、まず診察とカウンセリングから始まり、型取り、試適(仮合わせ)、完成、装着という流れで進みます。
治療期間はお口の状態や必要な調整回数によって異なりますが、一般的には2〜4週間程度で完成することが多いです。装着後も、違和感や痛みがあれば随時調整を行います。
入れ歯の作製には複数回の通院が必要となります。まず初回の診察で、お口の状態を確認し、入れ歯の種類や設計を決定します。次に型取りを行い、その後、仮合わせを経て最終的な入れ歯を装着します。
装着後も定期的なメンテナンスや調整が必要です。特に新しい入れ歯に慣れるまでは、違和感や痛みを感じることもありますので、遠慮なく歯科医師に相談しましょう。
保険適用入れ歯のメリット・デメリット
保険適用の入れ歯には、メリットとデメリットがあります。ご自身に合った選択をするために、それぞれの特徴をよく理解しておきましょう。
保険適用入れ歯のメリット
保険適用の入れ歯の最大のメリットは、費用の負担を大きく抑えられる点です。保険が適用されることで、自己負担額は自由診療に比べて大幅に軽減されます。
加えて、保険適用の入れ歯は比較的短期間で製作できるため、急に歯を失ってしまった場合でも迅速に対応できるという利点があります。
さらに、取り扱いがシンプルである点も大きな特徴です。初めて入れ歯を使う方でも扱いやすく、日常生活に大きな影響を与えずに使用できることから、幅広い年代の方にとって安心して利用できる選択肢となっています。
保険適用入れ歯のデメリット
一方で、保険適用の入れ歯にはいくつかのデメリットも存在します。まず、使用できる材料や設計に制限があるため、見た目や装着感に関しては自費診療の入れ歯に比べると劣る場合があります。
特に部分入れ歯の場合、金属のバネが見えることがあるため、前歯に使用する場合は審美的な懸念が生じることもあります。また、レジン素材のため、食べ物の温度を感じにくいという特徴もあります。
耐久性についても、保険適用の入れ歯は自費診療の入れ歯に比べると劣る傾向があり、3〜5年程度で作り直しが必要になることも少なくありません。
さらに、装着感や違和感については個人差がありますが、一般的に自費診療の入れ歯に比べると厚みがあり、違和感を感じやすい傾向があります。
自費診療の入れ歯との比較
保険適用の入れ歯と自費診療の入れ歯には、素材や設計、費用などに大きな違いがあります。それぞれの特徴を比較してみましょう。
自費入れ歯の種類と特徴
自費診療の入れ歯には、金属床義歯やノンクラスプデンチャーなど多様な選択肢があります。見た目の自然さや装着感、耐久性に優れ、保険の入れ歯に比べて快適性が高いのが特徴です。
金属床義歯は、入れ歯の床の部分に金属(チタンやコバルトクロムなど)を使用した入れ歯です。金属は熱伝導性に優れているため、食べ物の温度をダイレクトに感じることができます。また、金属は強度が高いため、床を薄く作ることができ、装着感も良好です。
ノンクラスプデンチャーは、金属のバネ(クラスプ)を使わない部分入れ歯です。歯ぐきと同じような色の樹脂でできているため、装着しても目立ちにくく、審美性に優れています。
費用・素材・仕上がりの違い
保険適用の入れ歯は費用を抑えられる反面、素材や仕上がりに制限があります。一方、自費の入れ歯は高品質な素材を用いるため費用は高額ですが、自然な見た目や長期的な使用に適しているといえます。
費用面では、保険適用の入れ歯が部分入れ歯で5,000円〜15,000円、総入れ歯で10,000円〜20,000円程度なのに対し、自費診療の入れ歯は金属床義歯で30万円〜60万円、ノンクラスプデンチャーで15万円〜30万円程度と大きな開きがあります。
素材や仕上がりについても、保険適用の入れ歯はレジン(プラスチック)が主体で、設計や形状に制限があるのに対し、自費診療の入れ歯は金属やより高品質な樹脂を使用し、患者さんの口腔内に合わせたオーダーメイドの設計が可能です。
選択時のポイント

入れ歯を選ぶ際は、費用だけでなく、ご自身のライフスタイルや優先したい点(見た目・快適さ・耐久性など)を考慮することが大切です。
例えば、人前に出る機会が多く、見た目を重視したい方は、金属のバネが見えないノンクラスプデンチャーなどの自費診療の入れ歯が適しているかもしれません。一方、費用を抑えたい方や、とりあえず機能回復を優先したい方には、保険適用の入れ歯が選択肢となるでしょう。
また、年齢や口腔内の状態、将来的な歯の喪失リスクなども考慮し、長期的な視点で選択することも重要です。どのような入れ歯が最適かは、歯科医師との十分な相談の上で決めることをおすすめします。
入れ歯のメンテナンスと長持ちさせるコツ
入れ歯は適切なケアを行うことで、快適に長く使用することができます。日常的なメンテナンスと定期的な専門的ケアについて解説します。
日常のお手入れ方法
入れ歯は毎日のお手入れが非常に重要です。食後には入れ歯を外して水で軽くすすぎ、食べかすを取り除きましょう。
入れ歯専用のブラシを使って、入れ歯の表面や裏側、バネの部分などを丁寧に清掃します。このとき、通常の歯ブラシは硬すぎるため、入れ歯専用の柔らかいブラシを使用することをおすすめします。
洗浄剤を使用する場合は、入れ歯専用の洗浄剤を使い、説明書に従って正しく使用しましょう。一般的な歯磨き粉は研磨剤が含まれているため、入れ歯の表面に傷をつける可能性があり、避けた方が良いでしょう。
定期的な歯科検診の重要性
入れ歯は時間の経過とともに、お口の状態が変化することで合わなくなることがあります。定期的に歯科医院を受診し、入れ歯の状態や適合性をチェックしてもらうことが重要です。
特に新しい入れ歯を装着した後の数か月間は、お口の状態が変化しやすいため、定期的な調整が必要になることがあります。違和感や痛みを感じたら、我慢せずに早めに歯科医師に相談しましょう。
また、残っている自分の歯のケアも重要です。部分入れ歯の場合、バネをかける歯が虫歯や歯周病になると、入れ歯の安定性に影響します。自分の歯も含めた口腔内全体のケアを心がけましょう。
入れ歯の寿命と交換時期
保険適用の入れ歯の平均的な寿命は3〜5年程度と言われています。しかし、適切なケアと定期的なメンテナンスを行うことで、より長く使用することも可能です。
入れ歯の交換が必要なサインとしては、「噛みにくい」「痛みがある」「入れ歯がグラつく」「話しにくい」などがあります。このような症状を感じたら、歯科医師に相談しましょう。
また、入れ歯の破損や変形が生じた場合も、早めに修理や交換を検討する必要があります。放置すると、お口の状態が悪化したり、さらなる問題を引き起こす可能性があります。
まとめ:あなたに合った入れ歯選びのために
入れ歯の保険適用と費用相場について詳しく解説してきました。保険適用の入れ歯は、費用を抑えながら基本的な機能を回復できる点が大きなメリットです。一方で、素材や設計に制限があるため、見た目や装着感には個人差があります。
入れ歯選びで大切なのは、ご自身のライフスタイルや優先したい点を明確にし、歯科医師と十分に相談することです。費用だけでなく、長期的な使用感や快適性も考慮して選択しましょう。
また、入れ歯は定期的なメンテナンスと適切なケアが欠かせません。日常的なお手入れと定期検診を習慣化することで、入れ歯を長く快適に使用することができます。
入れ歯に関するお悩みやご質問は、ぜひ専門医にご相談ください。私たちくろさき歯科では、患者さん一人ひとりに合わせた最適な入れ歯治療をご提案しています。お気軽にご相談ください。
院長・監修医師
黒崎 俊一(kurosaki syunichi)
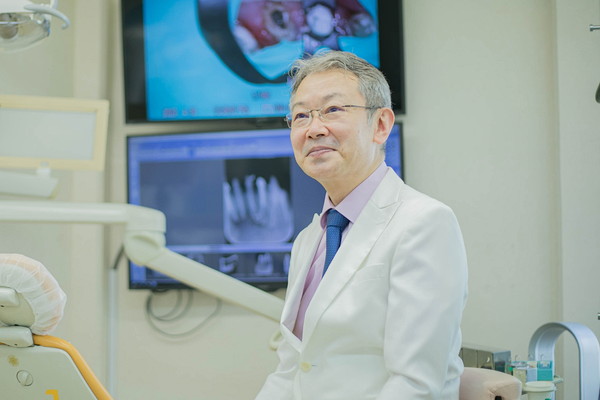
歯学博士/日本補綴歯科学会「専門医」
経歴・資格
-
1987年(昭和62年) 日本大学歯学部 卒業
-
1992年(平成4年) 日本大学大学院 歯学部 補綴専攻 修了・歯学博士取得
-
1996年(平成8年) くろさき歯科 開院(当院開業)
-
日本補綴歯科学会認定「専門医」/日本歯科審美学会会員/日本矯正歯科学会会員
-
日本大学歯学部 兼任講師として教育にも従事