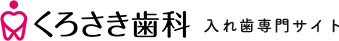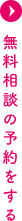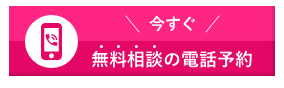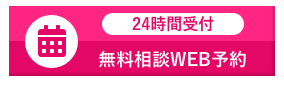入れ歯治療の流れと期間〜初診から装着までを専門医が解説
入れ歯治療を始める前に知っておきたいこと

入れ歯治療は、歯を失った方の噛む機能や見た目を回復する大切な治療法です。しかし、「入れ歯はどのように作られるのか」「治療期間はどのくらいかかるのか」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
入れ歯治療は単に型を取って装置を作るだけではありません。患者さんのお口の状態や生活習慣、ご希望に合わせて、丁寧に調整を重ねていく過程が必要です。
私は補綴専門医として長年入れ歯治療に携わってきましたが、患者さんが治療の流れを理解していることで、より満足度の高い結果につながることを実感しています。この記事では、入れ歯治療の流れと期間について、専門医の立場から詳しく解説していきます。
入れ歯治療の全体的な流れ
入れ歯治療は大きく分けて5つのステップで進みます。それぞれの段階で丁寧な対応が必要であり、それが最終的な入れ歯の出来栄えに大きく影響します。
まず初診では、お口の状態を詳しく診査し、患者さんのご希望をしっかりとお聞きします。この時点で、どのような入れ歯が適しているかの大まかな方向性が決まります。
次に、お口の中の準備を行います。これは入れ歯を入れる前に必要な処置で、残っている歯の治療や、場合によっては抜歯などが含まれます。
そして実際に入れ歯を作製していきます。精密な型取りから始まり、何度か試適を繰り返して、最終的な入れ歯が完成します。
入れ歯が完成したら装着し、微調整を行います。その後も定期的なメンテナンスが必要です。
このような流れで治療は進みますが、患者さんのお口の状態や入れ歯の種類によって、具体的な期間や回数は変わってきます。
初診・診断の重要性
入れ歯治療の第一歩は、詳細な診査と診断です。この段階でしっかりとした計画を立てることが、後の治療をスムーズに進める鍵となります。
初診では、レントゲン撮影や口腔内の検査を行い、残っている歯の状態や歯茎の健康状態、噛み合わせなどを総合的に確認します。また、患者さんの生活習慣や食事の好み、入れ歯に対する希望なども詳しくお聞きします。
この時点で「部分入れ歯」か「総入れ歯」か、また保険診療で対応するか自費診療にするかなど、大まかな方針を決めていきます。
どうですか?ご自身の希望や生活スタイルをしっかり伝えることが、満足のいく入れ歯を作るための第一歩です。
口腔内の準備と前処置
入れ歯を入れる前に、お口の中を整えることが非常に重要です。これは入れ歯の土台となる部分を健康な状態にするための準備段階です。
具体的には、虫歯の治療や歯周病のケア、必要に応じて抜歯などを行います。特に部分入れ歯の場合は、残っている歯が支えとなるため、これらの歯の健康状態が入れ歯の安定性に直接影響します。
また、抜歯をした場合は歯茎の治癒を待つ必要があります。一般的には抜歯後1〜3ヶ月程度の治癒期間を設けますが、これは患者さんの回復状況によって個人差があります。
この準備段階が不十分だと、後々入れ歯が合わなくなったり、残存歯に負担がかかったりする原因になります。しっかりと時間をかけて準備することで、長く快適に使える入れ歯の基盤ができるのです。
入れ歯作製の詳細なプロセス

入れ歯の作製は精密な作業の連続です。一般的な流れとしては、型取り、咬合採得、試適、完成・装着という段階を踏みます。
まず型取りでは、お口の形状を正確に再現するための印象採得を行います。これは入れ歯の土台となる重要な工程です。
次に咬合採得では、上下の歯の噛み合わせの関係を記録します。この段階で噛み合わせの高さや位置を決定するため、非常に重要です。
私が特に重視しているのは、試適の段階です。仮の状態の入れ歯を実際に口に入れてみて、形や噛み合わせ、見た目などを確認します。この時点での患者さんのフィードバックが、最終的な入れ歯の満足度に大きく影響するのです。
精密な型取り(印象採得)
入れ歯作製の基礎となるのが、精密な型取りです。この工程では、専用のトレーと印象材を使って、お口の中の形状を正確に写し取ります。
印象材には様々な種類があり、患者さんの状態に合わせて最適なものを選択します。例えば、歯茎の状態が良好な場合はアルジネート印象材、より精密さが求められる場合はシリコン印象材などを使用することがあります。
当院では、必要に応じて2回の印象採得を行うこともあります。最初に概形を採り、それをもとに個人用のトレーを作製し、さらに精密な印象を取る方法です。これにより、より適合性の高い入れ歯を作ることができます。
型取りは数分で終わる比較的短い処置ですが、この精度が入れ歯全体の出来を左右する重要なステップです。
噛み合わせの記録(咬合採得)
噛み合わせの記録は、入れ歯が機能的に働くために欠かせない工程です。この段階では、上下の顎の関係を正確に記録します。
具体的には、ワックスなどの材料を用いて、適切な噛み合わせの高さや位置を決定します。この時、単に歯が当たるだけでなく、顔の表情や発音、さらには全身のバランスも考慮します。
私の経験では、噛み合わせが少しでもずれると、食事の際の不快感や発音障害、さらには顎関節の問題にまで発展することがあります。そのため、時間をかけて丁寧に記録を取ることが重要です。
また、この段階で人工歯の色や形も選択します。患者さんの年齢や顔の形、希望する見た目などを考慮して、最も自然に見える歯を選びます。
試適と調整の重要性
試適は、完成前の入れ歯を実際に装着して確認する大切な工程です。この段階で細かい調整を行うことで、最終的な入れ歯の快適性が大きく向上します。
試適では、入れ歯の安定性、噛み合わせ、発音のしやすさ、見た目などを総合的にチェックします。患者さんにも実際に噛んでいただいたり、話していただいたりして、違和感がないか確認します。
私は特に「仮義歯」の使用を重視しています。これは最終的な入れ歯を作る前に、一時的に使用する入れ歯です。仮義歯を数週間使用することで、実際の生活での不具合や改善点が明確になり、最終義歯に反映させることができます。
入れ歯は一度作ってしまうと大幅な修正が難しいため、この試適と調整の段階でしっかりと時間をかけることが、長く快適に使える入れ歯を作るポイントなのです。
入れ歯治療の期間と通院回数

入れ歯治療にかかる期間は、患者さんの状態や入れ歯の種類によって大きく異なります。一般的な目安をお伝えしますが、個人差があることをご理解ください。
標準的な入れ歯治療の場合、初診から装着までは約1〜2ヶ月程度かかることが多いです。これは前処置が必要ない理想的な状況での期間です。
しかし実際には、抜歯や歯周病治療などの前処置が必要な場合が多く、その場合は治療期間が3〜6ヶ月程度に延びることもあります。特に抜歯後は歯茎の治癒を待つ必要があるため、時間がかかります。
通院回数についても、標準的な入れ歯治療では5〜7回程度が目安となりますが、調整の回数や前処置の有無によって増減します。
部分入れ歯の治療期間
部分入れ歯の場合、残存歯の状態が治療期間に大きく影響します。残っている歯に問題がなければ、比較的スムーズに進みます。
標準的な部分入れ歯治療の流れは以下のようになります。
まず初診・診断で1回、残存歯の治療が必要な場合はその回数(状態によって異なる)、型取りで1回、咬合採得で1回、試適で1〜2回、装着で1回、調整で2〜3回程度です。
全体としては、前処置がない理想的な状況で約1〜2ヶ月、前処置が必要な場合は3〜4ヶ月程度かかることが一般的です。
ただし、これはあくまで目安であり、複雑な症例や精密な調整が必要な場合は、さらに時間がかかることもあります。
総入れ歯の治療期間
総入れ歯(総義歯)の場合は、すべての歯がない状態での治療となるため、部分入れ歯とは異なる特性があります。
標準的な総入れ歯治療の流れは、初診・診断で1回、抜歯などが必要な場合はその回数、型取りで1〜2回、咬合採得で1回、試適で1〜2回、装着で1回、調整で3〜4回程度です。
総入れ歯は特に安定させることが難しいため、装着後の調整回数が部分入れ歯よりも多くなる傾向があります。全体の期間としては、前処置がない場合で約1.5〜2ヶ月、前処置が必要な場合は4〜6ヶ月程度かかることが一般的です。
私の臨床経験では、特に初めて総入れ歯を使用する方は、慣れるまでに時間がかかることが多いです。そのため、装着後のフォローアップを丁寧に行うことが重要だと考えています。
即日入れ歯と通常の入れ歯の違い
「即日入れ歯」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。これは抜歯直後に装着する仮の入れ歯のことで、通常の入れ歯とは異なる特徴があります。
即日入れ歯は、抜歯当日に装着できるため、見た目の空白期間がないというメリットがあります。特に前歯部の抜歯では、審美的な理由から即日入れ歯を希望される方が多いです。
しかし、即日入れ歯はあくまで「仮の入れ歯」です。抜歯後は歯茎が徐々に変化していくため、時間の経過とともに合わなくなっていきます。そのため、通常は3〜6ヶ月程度使用した後、歯茎の形状が安定してから最終的な入れ歯を作製します。
即日入れ歯と通常の入れ歯では、精度や耐久性、快適性に違いがあることを理解しておくことが大切です。即日入れ歯は一時的な解決策であり、最終的には通常の入れ歯作製のプロセスを経ることをお勧めします。
入れ歯装着後のケアとメンテナンス
入れ歯治療は装着して終わりではありません。長く快適に使い続けるためには、適切なケアとメンテナンスが欠かせません。
まず、新しい入れ歯に慣れるには時間がかかります。特に初めて入れ歯を使用する方は、1〜2週間程度の順応期間が必要です。この間は違和感や軽い痛みを感じることもありますが、徐々に改善していきます。
日々のケアとしては、入れ歯専用ブラシでの清掃と、就寝時の取り外しが基本です。入れ歯洗浄剤も効果的ですが、使用方法を守ることが重要です。
そして何より大切なのが、定期的な歯科医院でのメンテナンスです。入れ歯は時間の経過とともに合わなくなることがあるため、半年に1回程度のチェックをお勧めします。
入れ歯への順応期間

新しい入れ歯に慣れるまでには個人差がありますが、一般的には1〜2週間程度かかります。この期間は「順応期間」と呼ばれ、誰もが経験する自然なプロセスです。
順応期間中は、違和感や発音のしづらさ、軽い痛みなどを感じることがあります。特に総入れ歯の場合は、食事の味覚が変わったように感じることもあります。
これらの不快感は徐々に改善していきますが、あまりにも強い痛みや違和感が続く場合は、調整が必要かもしれません。遠慮なく歯科医院に相談しましょう。
私がいつも患者さんにお伝えしているのは、「最初は少しずつ慣れていくこと」の重要性です。柔らかい食べ物から始めて徐々に硬いものに挑戦したり、鏡を見ながら発音の練習をしたりすることで、順応がスムーズになります。
日常的なお手入れ方法
入れ歯を長持ちさせるためには、毎日の適切なお手入れが欠かせません。基本的なケア方法をご紹介します。
まず、食後は入れ歯を取り外して水で軽くすすぎます。これだけでも食べかすの付着を防ぐことができます。
1日1回は入れ歯専用ブラシを使って丁寧に清掃しましょう。通常の歯ブラシは硬すぎるため、入れ歯に傷をつける可能性があります。洗浄の際は、洗面台に水を張るか、タオルを敷くなどして、万が一落としても破損しないよう注意してください。
また、就寝時は必ず入れ歯を外し、入れ歯洗浄剤に浸けておくことをお勧めします。これにより、口腔内と入れ歯の両方を休ませることができます。
入れ歯洗浄剤を使用する際は、説明書の使用方法を必ず守ってください。長時間の浸漬や熱湯での消毒は、入れ歯の変形や劣化の原因になります。
定期的なメンテナンスの重要性
入れ歯は時間の経過とともに、口腔内の変化や材質の劣化により合わなくなることがあります。そのため、定期的な歯科医院でのメンテナンスが非常に重要です。
一般的には、半年に1回程度のチェックをお勧めしています。このチェックでは、入れ歯の適合状態や噛み合わせ、材質の劣化などを確認し、必要に応じて調整や修理を行います。
また、残存歯がある場合は、それらの歯のケアも同時に行うことが大切です。部分入れ歯の支えとなる歯が虫歯や歯周病になると、入れ歯全体の安定性に影響します。
私の臨床経験では、定期的なメンテナンスを受けている患者さんは、入れ歯の寿命が明らかに長く、トラブルも少ない傾向があります。「問題がないから」と受診を先延ばしにせず、定期的なチェックを習慣にしていただくことをお勧めします。
入れ歯は適切なケアとメンテナンスによって、5〜7年、場合によっては10年以上使用することも可能です。大切な投資として、日々のケアと定期的なメンテナンスを心がけましょう。
まとめ:快適な入れ歯生活のために
入れ歯治療は、初診から装着、そして装着後のケアまで、一連の流れの中で行われる総合的な治療です。標準的な治療期間は1〜2ヶ月ですが、前処置が必要な場合はさらに長くなることもあります。
治療の成功には、歯科医師の技術はもちろんのこと、患者さん自身の協力も欠かせません。特に試適段階での率直なフィードバックや、装着後の適切なケアが重要です。
入れ歯に完全に慣れるまでには時間がかかりますが、適切な調整と日々のケアによって、快適な入れ歯生活を送ることができます。何か不安や疑問があれば、遠慮なく歯科医師に相談してください。
私たちくろさき歯科では、患者さん一人ひとりのお口の状態や生活習慣に合わせた、オーダーメイドの入れ歯治療を提供しています。入れ歯でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。専門的な知識と経験を活かし、快適な入れ歯生活をサポートいたします。
院長・監修医師
黒崎 俊一(kurosaki syunichi)
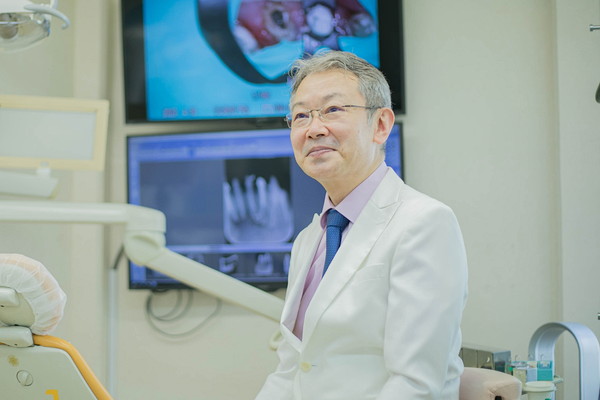
歯学博士/日本補綴歯科学会「専門医」
経歴・資格
-
1987年(昭和62年) 日本大学歯学部 卒業
-
1992年(平成4年) 日本大学大学院 歯学部 補綴専攻 修了・歯学博士取得
-
1996年(平成8年) くろさき歯科 開院(当院開業)
-
日本補綴歯科学会認定「専門医」/日本歯科審美学会会員/日本矯正歯科学会会員
-
日本大学歯学部 兼任講師として教育にも従事