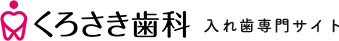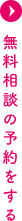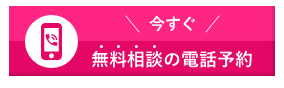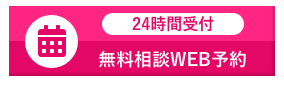入れ歯は何歳から必要?平均年齢と早期対応のメリット

入れ歯が必要になる年齢とは?日本人の平均値
入れ歯というと高齢者が使用するイメージをお持ちの方も多いかもしれません。しかし実際には、年齢に関係なく歯を失った際の治療選択肢として幅広い世代で利用されています。
厚生労働省の調査によると、日本人の歯の平均残存数は年齢とともに減少していきます。45歳以上から歯の数が28本(親知らずを除く健康な歯の基準)を下回り始め、60歳代で大きく減少することがわかっています。
具体的な年齢別の平均残存歯数は以下のようになっています:
- 15~24歳:28.0本
- 25~34歳:28.6本
- 35~44歳:28.1本
- 45~54歳:26.4本
- 55~64歳:23.3本
- 65~74歳:19.2本
- 75歳以上:13.3本
このデータから見ると、日本人が入れ歯を必要とする平均年齢は50歳前後からと考えられます。特に60歳前後から部分入れ歯の使用が増加する傾向にあります。
入れ歯が必要になる主な原因
入れ歯が必要になるのは、歯を失うことが直接の原因です。では、日本人が歯を失う主な理由は何でしょうか。
歯を失う原因第1位は「歯周病」です。歯周病は進行する過程で歯ぐきや顎の骨が破壊されていく病気です。自覚症状に乏しく、気づいた頃には重症化していることも珍しくありません。
歯周組織が歯を支えきれなくなると、抜歯を余儀なくされます。歯周病の末期では、歯が自然脱落することもあるのです。
第2位は「虫歯」です。虫歯は、ミュータンス菌に代表される虫歯菌の酸によって、エナメル質や象牙質が溶解していく病気です。軽度から中等度の虫歯なら保存できますが、重度の虫歯では抜歯が第一選択となりやすいです。
また、転倒などによる顔面への外傷も歯を失う原因となります。特に歯根が折れると、歯の保存が難しくなり、抜歯せざるを得なくなるケースが多いです。
令和4年度の歯科疾患実態調査によると、歯周ポケット(4mm以上)を有する者の割合は全体で58%にも上ります。年齢とともに増える傾向にあり、65〜74歳では56.2%、75歳以上で56.0%となっています。
しかし、若年層の15〜24歳でも約2割が歯周ポケットを持っており、歯周病への早期対策の必要性を再確認させる結果となっています。
若い世代の入れ歯事情

「入れ歯は高齢者だけのもの」というイメージを持っている方も多いでしょう。しかし、実際には30代や40代で部分入れ歯が必要になるケースもあります。
主な原因としては、重度の虫歯や歯周病の放置、外傷による歯の欠損などが挙げられます。特に、忙しさから定期検診を受ける機会を逃し、口腔内のトラブルを放置したまま悪化させてしまうと、抜歯が必要な状態にまで至ることがあります。
若い世代で入れ歯を付けることには心理的抵抗もあるでしょう。
しかし、欠損をそのままにしておくと、周囲の歯に大きな負担がかかり、さらに歯を失うリスクを高めることにもつながります。早い段階で適切な治療を受け、必要であれば入れ歯を装着することで、逆に将来にわたって多くの歯を守ることにもなるのです。
入れ歯の利用に年齢制限はありません。「自分はまだ入れ歯を使うには若いのでは?」と思う方もいますが、年齢に基づく制限は存在しないのです。
また、若い時期は歯肉の土手部分がしっかりしているため、入れ歯の安定性も高いという利点があります。
若い世代ほど入れ歯に対する抵抗感を持つ人も多く、その理由として「高齢者のイメージ」や「金属の引っ掛けが見える」という点が挙げられます。一方で、インプラントは治療費の高さや手術が必要であるため、踏み切れない人もいます。
入れ歯の種類と選び方
入れ歯には大きく分けて総入れ歯と部分入れ歯の2種類があります。総入れ歯は歯が一本も残っていないケースで使用し、部分入れ歯は自分の歯が一部残っている場合に使用します。
素材や構造、固定方法によっていろいろなタイプがあり、最近では金属床を使った薄型の入れ歯や、目立ちにくいノンクラスプデンチャーといったものも開発され、より快適さや審美性を求める傾向が高まっています。
保険診療の入れ歯
保険診療の入れ歯は、人工歯と義歯床が歯科用プラスチック(レジン)で作られています。原材料費が安い反面、摩耗や変色が起こりやすく、破折しやすいというデメリットがあります。
部分入れ歯の場合は、残った歯に引っ掛けるクラスプ(金属のバネ)が付随するため、見た目があまり良くありません。
しかし、壊れた時に修理がしやすい、治療期間が比較的短い、3割負担で5,000~15,000円程度で作製できるといったメリットがあります。気軽に作れる入れ歯として今も昔も高い人気を集めています。
自費診療の入れ歯
自費診療の入れ歯では、使用できる材料に制限がかかりません。例えば、人工歯にセラミックを使ったり、シリコーンのようなやわらかい素材でプレート部分を覆ったりすることも可能です。
その中でも特に人気が高いのがノンクラスプデンチャーです。保険診療では金属製のクラスプを使わなければならないところを、自費診療ならクラスプのない設計で部分入れ歯を作製できるからです。
クラスプの部分は歯ぐきと同じ色をしたやわらかい素材で構成されていることから、見た目も装着感も良好です。
ただし、自費診療の入れ歯は費用が高い、故障した時の修理が難しい、特別な製法が適応される場合は治療期間が長くなるといったデメリットもあります。
若くから入れ歯にするメリット
入れ歯の利用に年齢制限はないことが理解できたところで、若くから入れ歯にするメリットを紹介します。
1. 慣れるまでの時間を短縮できる
入れ歯を装着すると、粘膜に直接接触するため、初めは口の中に違和感を感じることがあります。若いうちから使用を始めることで、この違和感に早く慣れることができます。
年齢を重ねるほど新しいものへの適応力は低下する傾向にあるため、若いうちに入れ歯に慣れておくことは大きなメリットとなります。
2. ほうれい線が目立ちにくくなる
歯を失うと、顔の筋肉や皮膚を内側から支える構造が減少します。これにより、頬がこけたり、ほうれい線が深くなったりする可能性があります。
入れ歯を装着することで、失った歯の部分を補い、顔の形状を維持することができます。結果として、若々しい外見を保つことにつながります。
3. 入れ歯が安定しやすい
若い時期は歯肉の状態が良く、骨の吸収も少ないため、入れ歯が安定しやすい傾向にあります。また、唾液の分泌量も多いため、入れ歯の吸着力が高まり、装着感も良好です。
年齢を重ねると、歯肉の退縮や骨の吸収が進み、入れ歯が安定しにくくなることがあります。若いうちから入れ歯を使用することで、より快適な状態で使い始めることができるのです。

入れ歯装着を遅らせるための予防対策
入れ歯を付ける平均年齢を上げる(=できるだけ歯を失わずに長く自分の歯を残す)ためには、日々の予防が不可欠です。
特に歯周病は、日本人の歯を失う最大の原因とされており、歯周ポケットのケアや歯石除去、定期的な歯科検診が何よりも重要です。
歯周病は痛みが少ないまま進行する場合があり、気がついたときには歯を支える骨が溶けてしまっていることもあります。
どうですか?あなたは定期的に歯科検診を受けていますか?
予防のためには、以下の点に注意することが大切です:
- 毎日の丁寧な歯磨き(特に就寝前)
- フロスや歯間ブラシによる歯間清掃
- 定期的な歯科検診(最低でも年に2回)
- プロフェッショナルクリーニングの受診
- バランスの良い食生活
- 喫煙習慣がある場合は禁煙を検討
これらの予防策を継続することで、歯の寿命を延ばし、入れ歯が必要になる年齢を遅らせることができます。
「予防は治療に勝る」という言葉がありますが、歯科においてこれは特に真実です。
入れ歯とインプラントの比較
歯を失った場合の治療法としては、入れ歯の他にインプラントという選択肢もあります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、比較してみましょう。
入れ歯のメリット・デメリット
入れ歯のメリットとしては、手術が不要であること、比較的短期間で治療が完了すること、費用が比較的安価であることなどが挙げられます。特に保険適用の入れ歯であれば、経済的な負担は大きく軽減されます。
一方、デメリットとしては、装着時の違和感、発音や咀嚼機能の低下、定期的な調整や清掃が必要なことなどがあります。また、長期的には顎の骨が徐々に吸収されていくため、定期的な調整や作り直しが必要になることもあります。
インプラントのメリット・デメリット
インプラントのメリットは、天然歯に近い機能と見た目を実現できること、周囲の健康な歯を削る必要がないこと、骨の吸収を防ぐ効果があることなどです。固定式なので取り外しの手間もなく、違和感も少ないという特徴があります。
デメリットとしては、外科手術が必要なこと、治療期間が長いこと(通常3〜6ヶ月)、費用が高額であること(保険適用外)などが挙げられます。また、糖尿病や骨粗しょう症などの全身疾患がある場合や、喫煙習慣がある場合は、成功率が低下する可能性があります。
高額なインプラント、その前に進化していく入れ歯という選択肢もあります。特に最近の入れ歯は、従来のものと比べて格段に進化しており、見た目や機能性が向上しています。
まとめ:入れ歯と年齢の関係
入れ歯が必要になる平均年齢は50歳前後からですが、年齢に関係なく歯を失った際の治療選択肢として考えることができます。若くから入れ歯を使用することには、慣れるまでの時間短縮、ほうれい線予防、入れ歯の安定性向上などのメリットがあります。
一方で、できるだけ自分の歯を長く保つための予防対策も重要です。定期的な歯科検診や適切なオーラルケアを心がけることで、入れ歯が必要になる年齢を遅らせることができます。
入れ歯には保険適用のものから自費診療のものまで様々な種類があり、それぞれに特徴があります。ご自身の状況や希望に合わせて、最適な選択をすることが大切です。
歯の健康は全身の健康にも影響します。早めの対応と適切なケアで、いつまでも健康な口腔環境を維持していきましょう。
お口の健康に関するご相談は、いつでもくろさき歯科にお気軽にお問い合わせください。専門的な立場から、一人ひとりに最適なアドバイスをさせていただきます。
院長・監修医師
黒崎 俊一(kurosaki syunichi)
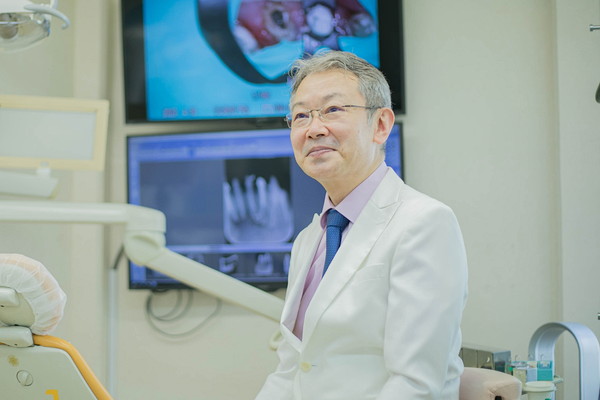
歯学博士/日本補綴歯科学会「専門医」
経歴・資格
-
1987年(昭和62年) 日本大学歯学部 卒業
-
1992年(平成4年) 日本大学大学院 歯学部 補綴専攻 修了・歯学博士取得
-
1996年(平成8年) くろさき歯科 開院(当院開業)
-
日本補綴歯科学会認定「専門医」/日本歯科審美学会会員/日本矯正歯科学会会員
-
日本大学歯学部 兼任講師として教育にも従事