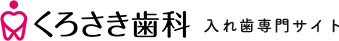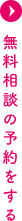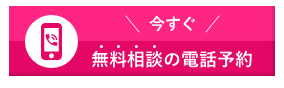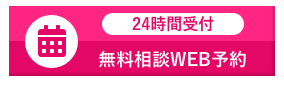入れ歯と差し歯の違いを徹底解説!選ぶ際の5つのポイント

入れ歯と差し歯の基本的な違いとは?
歯を失ったり、大きく損傷したりした場合、歯科治療で機能や見た目を回復することができます。その代表的な方法として「入れ歯」と「差し歯」があります。この二つは混同されがちですが、実は全く異なる治療法なのです。
入れ歯は、歯を完全に失った部分を補うための取り外し可能な装置です。一方、差し歯は歯の根が残っている状態で、その上に人工の歯冠を被せる治療法になります。
この違いは非常に重要です。なぜなら、どちらを選ぶかによって、治療期間、費用、メンテナンス方法、そして何より使用感が大きく変わってくるからです。
入れ歯の特徴とメリット・デメリット
入れ歯は、歯を失った部分を補うための取り外し可能な装置です。部分入れ歯と総入れ歯の2種類があり、それぞれ用途が異なります。
部分入れ歯は、一部の歯が失われた場合に使用され、残っている健康な歯にクラスプと呼ばれる金属のバネをかけて固定します。総入れ歯は、上顎または下顎のすべての歯を失った場合に使用される装置です。
入れ歯のメリット
入れ歯の最大のメリットは、外科的な処置が基本的に不要なことです。そのため、全身疾患をお持ちの方や高齢の方でも比較的負担が少なく治療を受けることができます。
また、取り外しが可能なので、就寝時に外して休ませることができますし、清掃も簡単です。保険適用の入れ歯であれば、費用面でも比較的負担が少ないという利点があります。
さらに、顔の形を整える効果もあるため、口元の印象が若々しくなることもあります。
入れ歯のデメリット
一方で、入れ歯には違和感を感じやすいというデメリットがあります。特に初めて使用する場合は、口の中に異物があるような感覚になり、慣れるまでに時間がかかることがあります。
また、噛む力が天然の歯の30〜40%程度しか出せないため、硬いものを噛みにくいという問題もあります。保険適用の入れ歯では、金属のバネが見えることもあり、審美性に不満を持つ方もいらっしゃいます。
定期的な調整や修理が必要なことも、入れ歯のデメリットの一つです。特に顎の骨は時間とともに変化するため、それに合わせて入れ歯も調整する必要があります。
差し歯の特徴とメリット・デメリット
差し歯は、歯の根が残っている状態で、その上に人工の歯冠を被せる治療法です。虫歯や外傷などで歯の大部分が失われても、歯根が健全であれば適用できます。
差し歯の治療では、まず残っている歯を削り、その上に土台を作ります。そして、その土台の上に人工の歯冠を装着します。素材には、保険適用のプラスチックや金属から、自費診療のセラミックやジルコニアまで様々な選択肢があります。
差し歯のメリット
差し歯の最大のメリットは、自然な見た目と使用感です。特に前歯の場合、セラミックなどの素材を使用すれば、天然歯とほとんど区別がつかないほど美しい仕上がりになります。
また、固定式なので取り外す必要がなく、違和感も少ないです。噛む力も天然歯に近いため、食事の制限も少なくて済みます。
さらに、周囲の健康な歯を削る必要がないため、他の歯への負担が少ないという利点もあります。
差し歯のデメリット
差し歯の最大のデメリットは、歯の根が健全でなければならないことです。歯周病などで歯根が弱っている場合は適用できないことがあります。
また、神経を取った歯に差し歯を装着する場合、歯が脆くなり、将来的に割れるリスクがあります。そのため、定期的な検診が欠かせません。
保険適用の差し歯では、素材や色の選択肢が限られるため、審美性に不満を持つ方もいます。特に奥歯の場合、保険適用では銀歯になることが多いです。

入れ歯と差し歯を選ぶ際の5つのポイント
入れ歯と差し歯、どちらを選ぶべきか迷ったときは、以下の5つのポイントを考慮するとよいでしょう。
1. 残存歯の状態
まず最も重要なのは、残っている歯の状態です。歯の根が健全に残っていれば差し歯が選択肢になりますが、歯根まで失っている場合は入れ歯かインプラントを検討することになります。
歯周病が進行している場合は、残存歯の状態や予後を考慮して治療法を選択する必要があります。
2. 審美性の重視度
見た目を重視する場合、特に前歯の治療では差し歯の方が自然な仕上がりになることが多いです。セラミックやジルコニアなどの素材を使用すれば、天然歯に近い透明感のある美しい歯を再現できます。
入れ歯の場合、特に保険適用のものは金属のバネが見えることがあり、審美性に課題があります。ただし、最近では金属を使わない入れ歯も増えてきており、選択肢が広がっています。
3. 費用と保険適用
費用面では、保険適用の治療を希望する場合、入れ歯も差し歯も基本的には保険が適用されます。ただし、素材や治療法によっては自費診療になることもあります。
保険適用の差し歯は、前から5番目までの歯は白い素材が使用できますが、それより奥は銀歯になることが多いです。審美性を重視する場合は、自費診療のセラミックなどを検討する必要があります。
4. 治療期間と通院回数
治療期間については、差し歯の方が比較的短期間で完了することが多いです。一般的に2〜3回の通院で治療が完了します。
入れ歯の場合、型取りから調整まで含めると4〜5回の通院が必要になることが多く、調整期間も含めるとやや長期間になります。
5. メンテナンスと長期的な管理
長期的な視点では、入れ歯は定期的な調整や洗浄が必要です。特に顎の骨は時間とともに変化するため、それに合わせて入れ歯も調整する必要があります。
差し歯は基本的にメンテナンスフリーですが、歯ぐきとの境目は虫歯になりやすいため、丁寧な歯磨きと定期検診が欠かせません。
インプラントという選択肢
入れ歯と差し歯以外にも、失った歯を補う方法としてインプラントという選択肢があります。インプラントは、人工の歯根を顎の骨に埋め込み、その上に人工の歯を装着する治療法です。
インプラントの最大の特徴は、天然歯に近い使用感と審美性です。固定式なので取り外す必要がなく、噛む力も天然歯とほぼ同等です。また、周囲の健康な歯を削る必要がないため、他の歯への負担も少なくなります。
ただし、インプラントは外科手術が必要であり、治療期間も長くなります。また、保険適用外の治療であるため、費用が高額になるというデメリットもあります。
インプラントを検討する前に、「高額なインプラント、その前に進化していく入れ歯という選択肢があります」という考え方も重要です。近年の入れ歯技術は大きく進歩しており、快適性や機能性が向上しています。
くろさき歯科での入れ歯・差し歯治療
くろさき歯科では、「第三世代の歯科治療®」という総合的な歯科医療アプローチを採用しています。これは単なる虫歯治療に留まらず、お口全体の健康を重視した治療法で、虫歯や歯周病の根本原因の解消と再発防止に焦点を当てています。
入れ歯治療においては、患者さん一人ひとりのお口の状態や生活スタイルに合わせたオーダーメイドの入れ歯を提供しています。従来の入れ歯の問題点を解決し、より快適に使用できる入れ歯の製作に力を入れています。
差し歯治療では、見た目の自然さと機能性を両立させた治療を心がけています。特に前歯の差し歯では、天然歯と見分けがつかないような美しい仕上がりを目指しています。
当院では、入れ歯、差し歯、インプラントなど、様々な選択肢の中から患者さんに最適な治療法を提案しています。無料相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
まとめ:自分に合った治療法を選ぼう
入れ歯と差し歯は、どちらも失った歯の機能と見た目を回復するための重要な治療法です。それぞれに特徴があり、一概にどちらが優れているとは言えません。
入れ歯は、歯根まで失った場合や広範囲の歯を失った場合に適しています。取り外しができるため清掃が容易で、費用面でも比較的負担が少ないというメリットがあります。
差し歯は、歯の根が残っている場合に選択できる治療法で、自然な見た目と使用感が特徴です。固定式なので違和感が少なく、噛む力も天然歯に近いというメリットがあります。
どちらを選ぶかは、残存歯の状態、審美性の重視度、費用、治療期間、メンテナンスの容易さなど、様々な要素を考慮して決める必要があります。
最適な治療法を選ぶためには、補綴治療を専門的に学んだ歯科医師との相談が欠かせません。くろさき歯科では、患者さん一人ひとりの状態や希望に合わせた最適な治療法を提案しています。お口の健康にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
お口の健康は、全身の健康や生活の質に大きく影響します。適切な治療を受けることで、美味しく食事を楽しみ、自信を持って笑顔で過ごせる毎日を取り戻しましょう。
詳しい情報や無料相談については、くろさき歯科までお気軽にお問い合わせください。経験豊富な歯科医師が、あなたのお口の健康をサポートいたします。
院長・監修医師
黒崎 俊一(kurosaki syunichi)
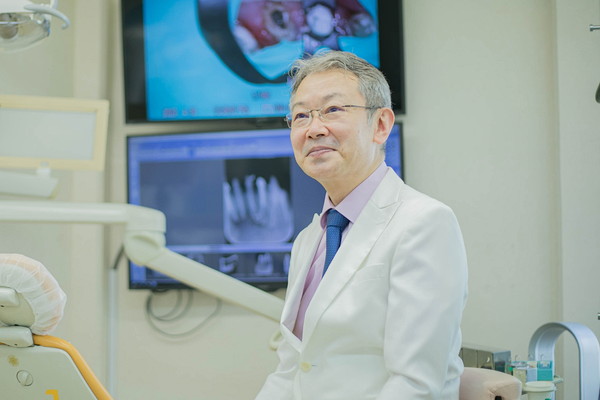
歯学博士/日本補綴歯科学会「専門医」
経歴・資格
-
1987年(昭和62年) 日本大学歯学部 卒業
-
1992年(平成4年) 日本大学大学院 歯学部 補綴専攻 修了・歯学博士取得
-
1996年(平成8年) くろさき歯科 開院(当院開業)
-
日本補綴歯科学会認定「専門医」/日本歯科審美学会会員/日本矯正歯科学会会員
-
日本大学歯学部 兼任講師として教育にも従事