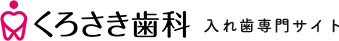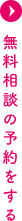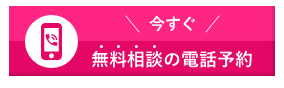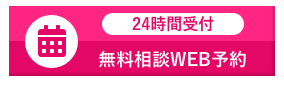【2025年最新】入れ歯の費用相場と選び方〜保険から自費まで徹底比較
入れ歯の種類と費用相場を知って最適な選択を

歯を失ってしまったとき、食事や会話に不便を感じるようになります。そんなとき頼りになるのが入れ歯です。入れ歯は失った歯の機能を回復させるだけでなく、お顔の形を整え、見た目の若々しさも取り戻してくれます。
しかし、入れ歯にはさまざまな種類があり、保険が適用されるものから自費診療のものまで、費用も大きく異なります。「どの入れ歯を選べばいいのか分からない」「予算に合った入れ歯を知りたい」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、2025年最新の入れ歯の種類と費用相場、それぞれのメリット・デメリットについて詳しく解説します。あなたに合った入れ歯選びのお役に立てれば幸いです。
入れ歯の基本と種類について
入れ歯(義歯)とは、歯を失った部分に人工の歯を補う治療法です。ブリッジやインプラントと並ぶ代表的な治療法であり、特に複数の歯を失った場合や顎全体にわたって歯がない場合に適しています。
入れ歯には大きく分けて「総入れ歯」と「部分入れ歯」の2種類があります。さらに、素材や構造の違いによって多くの種類が存在します。それぞれの特徴を見ていきましょう。
総入れ歯とは
総入れ歯は、上顎または下顎のすべての歯を失った場合に使用する入れ歯です。歯ぐきの形に合わせて作られた床(しょう)の上に人工歯が並べられています。
上顎の総入れ歯は吸着力が働くため比較的安定しますが、下顎の総入れ歯は舌の動きの影響を受けやすく、安定させるのが難しい傾向があります。最近では、吸着力を高める工夫やシリコン素材を使用することで、装着感を改善できるようになっています。
部分入れ歯とは
部分入れ歯は、一部の歯を失った場合に使用します。残っている自分の歯に金属のバネ(クラスプ)をかけて固定するのが一般的です。
部分入れ歯は残っている歯に負担をかけることがあるため、定期的なメンテナンスが必要です。また、金属のバネが見えることがあるため、審美面での配慮が必要な場合もあります。
最近では、金属のバネを使わないノンクラスプデンチャーなど、見た目に配慮した部分入れ歯も普及してきています。
保険適用の入れ歯について

保険適用の入れ歯は、健康保険が適用されるため費用を抑えることができます。基本的な機能を満たしていますが、素材や製作方法に制限があります。
保険適用入れ歯の費用相場
保険適用の入れ歯の自己負担額は、3割負担の場合で以下のような費用相場となります。
- 総入れ歯:約8,000円~23,000円
- 部分入れ歯:約4,000円~16,000円
これらの費用は歯科医院によって若干の違いがありますが、保険診療のため大きな差はありません。また、後期高齢者医療制度を利用している方は1割負担となるため、さらに費用を抑えることができます。
保険適用入れ歯のメリット・デメリット
保険適用の入れ歯には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット
- 費用が安く、経済的負担が少ない
- 製作期間が比較的短い
- どの歯科医院でも修理や調整が可能
デメリット
- 床が厚く、装着感に違和感を覚えることがある
- 金属のバネが見えることがある
- プラスチック素材のため、食べ物の温度を感じにくい
- 耐久性に限界がある(3~5年程度で作り直しが必要なことが多い)
保険適用の入れ歯は、費用面で大きなメリットがありますが、装着感や審美性、耐久性などに制限があります。そのため、より快適な入れ歯を求める方は、自費診療の入れ歯を検討することも選択肢の一つです。
自費診療の入れ歯の種類と特徴

自費診療の入れ歯は、保険適用外のため費用は高くなりますが、素材や製作方法に制限がないため、快適性や審美性、耐久性に優れた入れ歯を作ることができます。
2025年現在、人気の高い自費診療の入れ歯をいくつか紹介します。
金属床義歯
金属床義歯は、入れ歯の床の部分に金属(チタンやコバルトクロムなど)を使用した入れ歯です。金属は熱伝導性に優れているため、食べ物の温度をダイレクトに感じることができます。
また、金属は強度が高いため、床を薄く作ることができ、装着感も良好です。保険適用の入れ歯の約1/4の厚みで作れるため、違和感が少なく、より自然な装着感が得られます。
費用相場:部分入れ歯で30万~60万円、総入れ歯で50万~80万円程度
ノンクラスプデンチャー
ノンクラスプデンチャーは、金属のバネ(クラスプ)を使わない部分入れ歯です。歯ぐきと同じような色の樹脂でできているため、装着しても目立ちにくく、審美性に優れています。
金属アレルギーの方でも使用できるのが特徴です。ただし、強度は金属床義歯に比べるとやや劣るため、強く噛むと変形することがあります。
見た目が自然なのが最大の魅力です。人前でお話しする機会が多い方や、金属のバネが見えることに抵抗がある方に人気があります。
費用相場:8万~30万円程度
シリコン義歯(コンフォート・デンチャー)
シリコン義歯は、歯ぐきと接触する部分にシリコン素材を使用した入れ歯です。柔らかく弾力性があるため、歯ぐきにフィットしやすく、装着時の痛みを軽減できます。
噛む力が直接歯ぐきに伝わりにくいため、歯ぐきへの負担が少なく、長時間の使用でも疲れにくいのが特徴です。特に歯ぐきが痩せている方や、入れ歯の痛みに悩んでいる方におすすめです。
費用相場:部分入れ歯で10万~50万円、総入れ歯で40万~60万円程度
マグネット義歯
マグネット義歯は、磁石の力を利用して固定する入れ歯です。残っている歯の根に磁性アタッチメントを装着し、入れ歯側にも磁石を埋め込むことで、磁力によって安定させます。
バネを使わないため見た目が自然で、着脱も簡単です。ただし、適応できるケースが限られており、残存歯の状態によっては選択できないこともあります。
費用相場:マグネット1個につき約5万円、トータルで10万~60万円程度
高品質な入れ歯「コーヌスクローネ義歯」
コーヌスクローネ義歯(ドイツ式入れ歯)は、高品質な入れ歯の代表格です。残っている歯に金属の内冠を被せ、その上に外冠を持つ入れ歯をはめ込む構造になっています。
茶筒の原理を応用した構造で、内冠と外冠の間に生じる摩擦力によって強固に固定されます。バネを使わないため見た目が自然で、しっかりと固定されるため外れにくいのが特徴です。
長期的な使用を考えると、コストパフォーマンスに優れた選択肢といえます。ただし、初期費用は高額になります。
費用相場:50万円以上(本数によっては100万円を超えることもあります)
コーヌスクローネ義歯は、高い安定性と快適な装着感、優れた審美性を兼ね備えた高品質な入れ歯です。長期的な使用を考えている方や、入れ歯の快適性を最優先したい方におすすめです。
ただし、残存歯の状態によっては適応できないケースもあるため、歯科医師との相談が必要です。
入れ歯選びのポイント
入れ歯選びで迷ったときは、以下のポイントを参考にしてください。
予算と長期的なコスト
入れ歯は初期費用だけでなく、メンテナンスや将来的な作り直しなども考慮する必要があります。保険の入れ歯は初期費用は安いですが、耐久性の面で3~5年程度で作り直しが必要になることが多いです。
一方、自費の入れ歯は初期費用は高いものの、耐久性に優れているため長期的に見るとコストパフォーマンスが良い場合もあります。ご自身の予算と長期的な視点でコストを考えることが大切です。
装着感と快適性

毎日使うものだからこそ、装着感の良さは重要なポイントです。特に初めて入れ歯を使う方は、違和感に敏感です。
保険の入れ歯は床が厚いため違和感を覚えやすい傾向がありますが、自費の入れ歯は薄く作ることができるため、装着感が良好です。特にシリコン義歯は柔らかい素材を使用しているため、装着時の痛みが少ないのが特徴です。
見た目の自然さ
入れ歯の見た目は、日常生活の質に大きく影響します。特に前歯の入れ歯や、人前で話す機会が多い方は、見た目の自然さを重視したいところです。
保険の入れ歯は金属のバネが見えることがありますが、ノンクラスプデンチャーやマグネット義歯などの自費の入れ歯は、バネを使わないため見た目が自然です。
残存歯への負担
部分入れ歯の場合、残っている歯に負担をかけることがあります。特に金属のバネを使う保険の入れ歯は、バネをかける歯に負担がかかりやすいです。
マグネット義歯やコーヌスクローネ義歯などは、残存歯への負担が少ない設計になっているため、長期的な歯の保存を考えると良い選択肢です。
専門医によるカウンセリング
入れ歯選びで最も重要なのは、専門医によるカウンセリングです。お口の状態は一人ひとり異なるため、どの入れ歯が最適かは専門医の診断が必要です。
特に自費の入れ歯は種類が多く、それぞれ特徴が異なるため、ご自身の状態や希望に合った入れ歯を選ぶためには、専門医のアドバイスが欠かせません。
入れ歯専門の歯科医院では、初回相談に時間をかけて丁寧に説明してくれるところが多いので、不安な点はしっかり相談しましょう。
入れ歯のメンテナンスと長持ちさせるコツ
入れ歯を長く快適に使うためには、適切なメンテナンスが欠かせません。以下のポイントを押さえておきましょう。
日々のお手入れ
入れ歯は毎日使用した後、専用のブラシでしっかり洗浄することが大切です。特に歯と歯の間や、床と人工歯の境目は汚れがたまりやすいので、丁寧に洗いましょう。
洗浄後は、入れ歯洗浄剤に浸けておくと、細菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つことができます。ただし、金属部分がある入れ歯は、洗浄剤の種類に注意が必要です。
定期的な歯科検診
入れ歯は使っているうちに少しずつ合わなくなることがあります。これは、歯ぐきの形が変化したり、入れ歯自体が劣化したりするためです。
半年に1回程度の定期検診で調整してもらうことで、入れ歯を長く快適に使うことができます。また、残っている自分の歯のケアも忘れずに行いましょう。
入れ歯が合わないまま使い続けると、口内炎や歯肉炎の原因になることもあります。違和感や痛みを感じたら、早めに歯科医院を受診しましょう。
適切なメンテナンスを行うことで、入れ歯の寿命を延ばし、快適に使い続けることができます。
まとめ:あなたに合った入れ歯を見つけるために
入れ歯には保険適用のものから自費診療のものまで、さまざまな種類があります。それぞれに特徴やメリット・デメリットがあるため、ご自身の状態や希望、予算に合わせて選ぶことが大切です。
保険適用の入れ歯は費用面でのメリットがありますが、装着感や審美性、耐久性などに制限があります。一方、自費診療の入れ歯は初期費用は高いものの、快適性や審美性、耐久性に優れています。
入れ歯選びで迷ったときは、入れ歯専門の歯科医院でカウンセリングを受けることをおすすめします。専門医の診断とアドバイスを参考に、あなたに最適な入れ歯を見つけましょう。
さいたま市南区南浦和にあるくろさき歯科では、入れ歯専門の歯科医院として、患者さん一人ひとりに合った入れ歯を提案しています。日本補綴学会認定専門医である院長が、お口の状態だけでなく体全体のバランスも考慮した治療計画を立て、快適で長く使える入れ歯を提供しています。
入れ歯でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。無料相談も受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
詳しい情報は入れ歯 くろさき歯科のホームページをご覧ください。
院長・監修医師
黒崎 俊一(kurosaki syunichi)
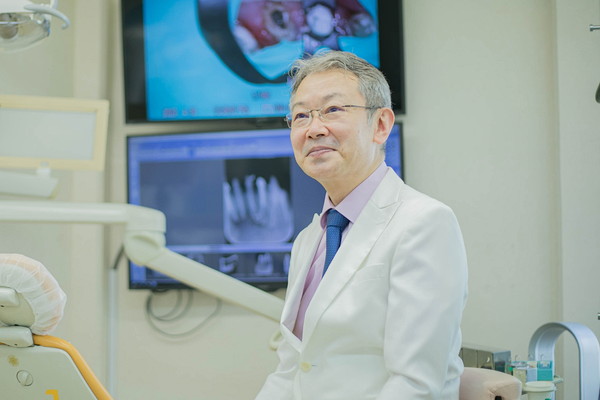
歯学博士/日本補綴歯科学会「専門医」
経歴・資格
-
1987年(昭和62年) 日本大学歯学部 卒業
-
1992年(平成4年) 日本大学大学院 歯学部 補綴専攻 修了・歯学博士取得
-
1996年(平成8年) くろさき歯科 開院(当院開業)
-
日本補綴歯科学会認定「専門医」/日本歯科審美学会会員/日本矯正歯科学会会員
-
日本大学歯学部 兼任講師として教育にも従事